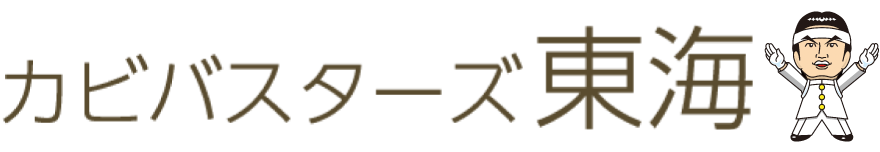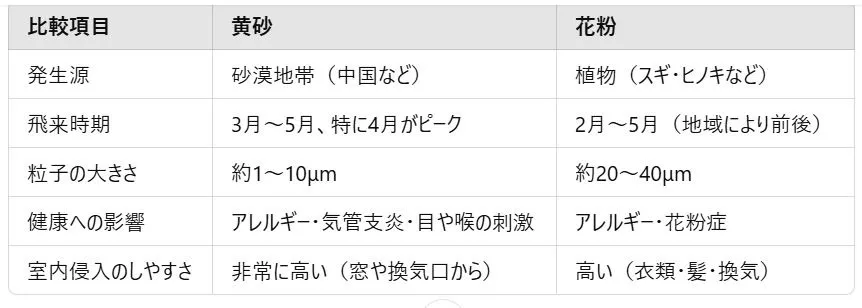知らなきゃ怖い!肺にカビが生えるリスクと対策
2025/02/08
知らなきゃ怖い!肺にカビが生えるリスクと対策
カビの健康被害とMIST工法®での安全な予防方法とは?
こんにちは、MIST工法®カビバスターズ東海のブログへようこそ。私たちは住環境に潜むカビの問題を専門的に解決し、皆さまの健康を守るお手伝いをしております。カビと聞くと、家の壁やお風呂場などの表面に生えるイメージが強いかもしれませんが、実はカビの胞子は空気中を漂い、さまざまな場所に付着・繁殖する可能性があります。そのため、日常生活の中でカビの存在を完全にゼロにするのは難しく、私たちが呼吸する空気の中にも微量なカビ胞子が混在していることがあります。
しかし、一般的に健康な人であれば、免疫力のおかげで少量のカビ胞子を吸い込んでも大きな問題に至ることはあまりありません。ところが、体調不良や免疫力が低下しているとき、また高齢者や小さなお子さんなどは、こうしたカビ胞子が肺や気道へ入り込み、深刻な感染症を引き起こすリスクが高まります。肺に生えたカビによる病気は「肺カビ感染症」や「アスペルギルス症」などと呼ばれ、その症状は咳、痰、息切れ、発熱など多岐にわたります。さらに放置してしまうと、肺機能の低下や他の器官への影響も出かねないため、早めの対処と予防が大切です。
私たちカビバスターズ東海では、MIST工法®という特殊な施工方法を用いて、カビの発生源を徹底的に洗浄・除去し、再発しにくい環境を整えるお手伝いをしております。空気中に舞うカビを抑え、建物の構造そのものを傷めないように配慮した施工が特徴です。カビが肺に生えるというと恐ろしく感じますが、正しい知識と対策を行うことで大切な家族や自分自身の健康を守ることができます。このブログでは、カビ被害の実例や対策方法について詳しくお伝えしてまいりますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
肺カビ感染症とは?
肺にカビが棲みつく現実を知ろう:感染のメカニズムとアスペルギルス症の深い関係
1. 肺にカビが繁殖するメカニズム
カビと聞くと、多くの人はジメジメしたお風呂場や壁紙の裏に生えるものを想像するかもしれません。しかし、実際にはカビの胞子は空気中に広く存在しており、私たちが呼吸をする際にはごく微量ながら常に吸い込んでいる可能性があります。通常、健康な体では免疫機能が働き、吸い込んだカビ胞子を排除したり無害化したりしますが、何らかの要因で免疫力が低下している場合や、肺に傷や病変がある場合は、体内に侵入したカビ胞子が肺の組織内で増殖してしまうことがあるのです。
このように肺内でカビが繁殖する現象を「肺カビ感染症」と呼ぶことがあります。カビ胞子は非常に微小で、気道を通り抜けて肺の奥深くの肺胞(はいほう)に達することが可能です。そこで適度な湿度と栄養がある環境に遭遇すると、カビが繁殖を始めてしまうわけです。さらに、カビの種類によっては繁殖力が強く、周辺組織を損傷したり、炎症を引き起こしたりするため、症状が重篤化しやすいケースも報告されています。
また、喫煙や過去の肺疾患などによって肺の機能が弱っている人は、カビを排除する力が低下しており、肺にカビが繁殖しやすくなるリスクが高まります。免疫不全状態(例えばステロイドや免疫抑制剤の使用、がん治療など)にある方や、高齢者、小さなお子さんなども注意が必要です。カビは植物のように光合成をするわけではなく、有機物を分解しながら成長するため、体内の組織を栄養源にして進行してしまうのが特徴です。こうした背景を理解しておくと、肺へのカビ感染を予防する対策の重要性や、早期発見・治療の必要性を一層認識できるでしょう。
2. 肺カビ感染症とアスペルギルス症の関係
肺カビ感染症のなかでも特に知られているのが「アスペルギルス症」です。アスペルギルス(Aspergillus)は、自然界に広く分布する糸状菌(カビ)の一種で、土壌や植物、建物の埃(ほこり)など、日常生活のあらゆる場所に存在しています。健康な人が少量のアスペルギルス胞子を吸い込んでも、通常は体内の免疫細胞が排除するため、ほとんど問題となりません。しかし、免疫力が落ちている人や慢性疾患を抱える人、長期入院患者、化学療法・放射線治療などを受けている方の場合は、アスペルギルス胞子が体内、特に肺胞内で増殖しやすくなり、感染症を引き起こすリスクが高まります。
アスペルギルス症にはいくつかの型がありますが、代表的なのは「侵襲性アスペルギルス症」と呼ばれる重篤なタイプです。侵襲性アスペルギルス症では、肺組織がカビによって侵されるだけでなく、血管を通じて全身へと広がってしまう恐れもあります。特に免疫不全の状態にある患者さんでは、適切な治療が行われないと生命を脅かす深刻な合併症を引き起こすことがあります。
また、比較的軽症のタイプとしては、既に肺に空洞(肺の組織が欠損して空間になった部分)がある患者さんにカビが住みつき「真菌ボール」と呼ばれる固まりを形成する場合もあります。これは慢性肺疾患などを抱えた方に見られることが多く、慢性的に咳や痰が続いたり、肺機能の低下を招いたりする可能性があります。症状が進行すると血痰が出るケースもあり、日常生活に大きな支障をきたすため、早期に専門医の受診と的確な治療が必要です。
このように、肺カビ感染症とアスペルギルス症は密接な関係があり、予防や早期対策の観点からも切り離して考えることはできません。カビというと見た目の汚れだけに注目しがちですが、体内に侵入して思わぬ病気を引き起こす可能性があることを改めて認識し、自宅や職場などのカビ対策を徹底して行うことが重要です。
肺カビ感染症の症状とリスク
カビによる呼吸器トラブルを見逃さないために:症状と免疫力低下のリスクを徹底解説
1. 咳・痰・息切れなどの代表的な症状
肺カビ感染症の初期症状としては、咳や痰、息切れなどが挙げられます。一見すると風邪や気管支炎と似たような症状に思えるため、カビが原因だと気づかれにくいという問題点があります。特に、咳が長引いたり、痰に血が混じるなどの異変が見られる場合は、単なる風邪ではない可能性を考慮し、医療機関での受診を検討することが大切です。肺の中でカビが繁殖すると、肺胞や気管支に炎症が起こり、呼吸機能が損なわれることで息切れや胸の痛みを感じるケースもあります。
また、悪寒や発熱など全身症状が現れる場合もあり、これらの症状が長期にわたって改善しない場合は、肺カビ感染症を含む真菌感染の疑いを持つことが必要です。特に免疫機能に問題のない健康な人であっても、過労やストレスなどで一時的に体力が低下しているときや、タバコなどの習慣によって肺が弱っているときには、カビに感染しやすくなるリスクが高まります。肺カビ感染症は、初期段階では症状があまり強く出ない場合もあるため、自己判断で放置してしまうと知らぬ間に病状が進行し、肺機能の一部が損なわれてしまうことがあるのです。
カビといえば、目に見える黒い斑点やカビ臭といったイメージが強いかもしれませんが、肺カビ感染症では体内で進行しているため、外からは発見しにくい特徴があります。そのため、日頃から慢性的な咳や痰が続く、呼吸が浅くなったように感じるといった症状には注意が必要です。もし、こうした症状が長引く場合には、内科や呼吸器科での検査を受けることで、早期発見・早期治療につながります。症状が軽い段階で対処をすれば、その後の健康被害を最小限に食い止めることができるため、自己判断に頼らず医師の診断を仰ぐことが重要です。
2. 免疫力が低下している方への影響
肺カビ感染症の最も大きなリスクグループとして挙げられるのが、免疫力が低下している方々です。免疫力は私たちの体を病原菌やウイルス、真菌(カビ)などから守る重要な機能ですが、加齢や病気、治療薬の副作用、過度なストレスなど、さまざまな要因で弱まることがあります。特に、がん治療で抗がん剤や放射線治療を受けている方、臓器移植後に免疫抑制剤を使用している方、慢性疾患によって体力が落ちている方などは、カビに対する抵抗力が通常よりも低くなりがちです。その結果、空気中に存在するカビ胞子を吸い込んだ際、健常者なら排除されるはずの微生物が肺や気管支に定着し、増殖を始めてしまうリスクが高まります。
さらに、こうした免疫力低下の状態で肺カビ感染症が発症すると、進行が早く、症状も重篤になりやすい点が問題です。肺の内部だけでなく、血管を介して全身へとカビが拡散してしまう「侵襲性真菌感染症」に進展する可能性もあり、ときには命に関わる深刻な事態に至ることもあります。また、慢性的に肺疾患を抱えている方が肺カビ感染症を併発した場合、肺の機能がさらに低下することで日常生活に影響を及ぼし、長期間にわたる治療や入院が必要になるケースも考えられます。
このように、免疫力が低下している方々は、カビによる感染症を発症する確率や、重篤化するリスクが高いため、一層慎重な環境管理と健康管理が求められます。室内の湿度を適正に保つ、定期的に換気を行う、カビの発生しやすい場所を清掃・消毒するなどの基本的なカビ対策はもちろん、少しでも肺に関係する症状が出た場合には早めに医療機関を受診することが重要です。特に、がん治療中や免疫抑制剤の服用中などで抵抗力が落ちているときは、かかりつけ医や専門医との連携を深め、予防的な視点からのケアを怠らないようにしましょう。こうした取り組みが、肺カビ感染症の重症化を防ぎ、健康な呼吸器機能を守るための大きな一歩となります。
カビが生えやすい環境と原因
カビの温床を作らないために:湿度や換気を見直して安全な生活空間を守ろう
1. 湿度・温度・換気不足が引き起こすカビ繁殖
カビが生えやすい空間を考える際に、まず注目したいのが「湿度・温度・換気」の3つの要素です。カビは高温多湿の環境で急激に繁殖する性質を持ち、室内の湿度が60%を超えると一気に増えやすくなると言われています。例えば、梅雨の時期や、冬場に暖房を長時間使うことで室内が蒸し暑くなる場合、窓を開ける機会が少なくなるため、空気がこもりやすく湿度が上昇しがちです。さらに温度が20〜30℃ほどに保たれると、カビにとって絶好の繁殖環境が整ってしまいます。
もう一つ見落としがちなのが換気不足です。換気が不十分な室内では、湿気がこもり、空気中の水分量が増えるだけでなく、室内の空気が循環しないためカビ胞子がとどまったままになります。お風呂場や台所など水をよく使う場所はもちろん、押入れやクローゼットの奥など、もともと風通しの悪いスペースは要注意です。さらに、エアコンを使用している場合でも、フィルターや内部にカビが生えていると、それらの胞子が空気中に拡散しやすくなります。定期的な掃除やフィルター交換を怠ると、知らぬ間にカビをばらまいているという事態にもなりかねません。
こうした環境が続くと、壁紙や家具の裏側、窓枠のゴムパッキンなど、普段あまり目にしない部分にカビが繁殖し、見た目には気付かないまま空気中の胞子が増加していくことがあります。結果として、室内に漂うカビ胞子を吸い込むリスクが高まり、アレルギー症状を引き起こしたり、免疫力が低下している方にとっては肺カビ感染症など重大な健康被害につながる可能性も否定できません。まずは適切な湿度管理、こまめな換気、そして定期的な掃除を心がけることで、カビの温床を作らない環境づくりを意識することが大切です。
2. カビ胞子を多く含む空間の見分け方
カビは目に見える形で発生している場合もあれば、表面にほとんど現れずに内部で静かに増殖している場合もあり、意外と発見が難しいケースがあります。そこで重要になるのが、「カビ胞子を多く含む空間の兆候を見分ける視点」を持つことです。例えば、部屋に入ったときに独特のカビ臭さを感じる場合は、すでに室内のどこかでカビが発生・繁殖している可能性が高いといえます。その他、壁紙の表面に小さな黒や緑の斑点がある、窓の結露がひどくサッシ部分に黒ずみがある、といった目視での確認も効果的です。
また、部屋の中で特定の場所だけが異様に湿っている感じがする場合や、風通しが悪くジメジメした空気がこもっているスペースも要注意です。押入れやクローゼット、シンク下や洗濯機周りなど、水まわりや密閉性の高い収納スペースは、カビが好む条件がそろいやすいのが特徴です。加えて、住まい自体の構造や立地によっては、壁の裏側や床下で結露や水漏れが発生し、気づかぬうちにカビの温床となっているケースもあります。表面上はキレイに見えても、内部に広がったカビを見落としてしまうと、その胞子を吸い込み続ける生活を余儀なくされることになりかねません。
さらに、エアコンや空気清浄機などのフィルターをチェックしてみると、意外にカビやホコリが溜まっていることがあります。カビ胞子は極めて小さいため、一度繁殖が進行すると空気の流れとともに部屋全体に拡散されてしまいます。その結果、家族全員が知らず知らずのうちにカビ胞子を吸い込むリスクが高まり、アレルギー症状や呼吸器のトラブルが出現する原因になります。日常的な点検や清掃を習慣化し、カビの兆候を早期に発見して対処することが、健康を守る最善策なのです。もし「これは怪しいかも」と感じたら、専門業者の点検を検討することも有効です。早めの行動で、カビの広範囲な繁殖や健康被害を未然に防ぎましょう。
日常生活での予防策
健康を守るために今日からできること:カビを寄せ付けない暮らしの基本ポイント
1. 室内の適切な湿度管理と換気の重要性
カビを防ぐうえで、まず押さえておきたいのが「湿度のコントロール」と「十分な換気」です。カビは高温多湿を好む性質を持ち、特に湿度が60%を超えた状態が続くと一気に繁殖しやすくなります。そのため、梅雨時期や雨の多い季節、あるいは冬場でも加湿器を使いすぎたり、日中あまり窓を開けない生活を続けていると、知らず知らずのうちに部屋の湿度が高まり、カビの温床を作り出してしまうことがあります。さらに、室内の温度が20〜30℃程度に保たれていると、カビにとって最適な環境となり、一度繁殖が始まると勢いがついてしまうのです。
こうした状況を防ぐためには、湿度計を用いて部屋の湿度を常にチェックし、おおむね40〜60%程度を維持するように心がけましょう。湿度が高いと感じるときは、こまめに窓を開けて換気を行ったり、除湿器やエアコンの除湿機能を活用すると効果的です。特にキッチンや浴室、洗濯物を乾かすスペースなど、水分を多く使う場所はこまめな換気が不可欠です。ドアを閉め切ったままにせず、使用後は窓や換気扇を回して湿気を溜め込まないように注意しましょう。
また、部屋のレイアウトによっては空気の流れが悪くなり、特定の場所に湿気がこもりやすいことがあります。家具を壁にぴったりとつけすぎると壁と家具の間に空気が流れにくくなり、カビが生えやすい隙間を作ってしまう原因にもなります。少しだけ余裕をもって家具を配置し、エアコンや扇風機などで空気を循環させる工夫をすると、湿度バランスの良い室内環境を保ちやすくなります。こうした小さな配慮の積み重ねが、カビだけでなくダニや様々な菌の繁殖を抑え、健康的で快適な住環境を維持するための大切なステップとなります。
2. 定期的な清掃・除湿でカビの発生を抑える
いくら湿度や温度を管理していても、部屋の隅々に埃(ほこり)や汚れが溜まっている状態では、カビの栄養源となる有機物が豊富に存在することになり、繁殖のリスクを高めてしまいます。そこで重要なのが、日常的な清掃と除湿の習慣です。まずは、床や棚の上だけでなく、押入れやクローゼットの内部、家具の裏側など、普段は見落としがちな場所もしっかりと掃除を行いましょう。溜まった埃やゴミを取り除くだけでなく、カビが発生していないか目視で確認しておくと、早期の発見につながります。
また、水回りの清掃も非常に大切です。浴室やキッチンのシンクまわり、洗濯機の排水口などは高い頻度で水や洗剤が使われるため、常に湿気がこもりやすく、カビが発生・拡散しやすいポイントです。洗剤やブラシを使っての定期的な洗浄はもちろん、使用後は換気扇を回したり、窓を開けるなどして空気の通り道を確保するように心がけましょう。洗濯物を部屋干しする際も、サーキュレーターやエアコンの除湿機能を活用して、できるだけ速やかに乾かすのが理想です。
さらに、押入れやクローゼットなどの収納スペースは、閉めっぱなしで空気が循環しない環境になるとカビの温床となりがちです。定期的に扉を開け放って風を通し、湿気が篭(こも)らないように注意すると同時に、すのこや除湿剤を利用するのも効果的です。特に日本の住宅では、気候や住宅構造の影響で押入れの奥や床下などに結露が発生しやすいケースがあり、それがカビを引き寄せる原因となります。気温や湿度の高い時期だけでなく、冬場やシーズンオフの衣類・布団をしまうときにも、こまめにチェックするクセをつけておくと安心です。
こうした清掃・除湿の取り組みは、一度だけまとめて行うよりも、日常的に継続することが何よりも大切です。少し面倒に感じるかもしれませんが、こまめに掃除や整理整頓をする習慣を身につけておけば、目に見えないところにカビが広がるのを未然に防ぎ、結果的には大掛かりな掃除やリフォームのリスクを減らすことにもつながります。日頃から部屋を清潔に保ち、湿度と汚れを管理することで、安心して過ごせる快適な生活空間を手に入れましょう。
MIST工法®によるプロのカビ対策
なぜMIST工法®なのか?専門家が行うカビ対策で安心と安全を手に入れよう
1. 徹底的な洗浄・除去と再発防止対策
MIST工法®によるカビ対策は、まず何よりも「徹底的な洗浄・除去」に重きを置いていることが特徴です。一般的なカビ対策では、目に見える範囲のカビを除去したり、漂白剤などで一時的に黒ずみを消すだけで終わってしまうケースが少なくありません。しかし、それでは壁紙や床材、家具などの素材の奥深くに根を張っているカビの菌糸まで完全に除去できず、結局は再発を繰り返してしまう原因となります。MIST工法®では、素材の内部まで浸透していく専用の薬剤や蒸気などを適切に使い分けることで、カビの目に見えない部分までしっかりとアプローチしていきます。
さらに、徹底的にカビを取り除いた後は、「再発防止」の対策も欠かしません。カビを取り除いても、湿度や温度、換気などの住環境の問題が解決されなければ、再び同じ場所にカビが発生するリスクが高まります。そこでMIST工法®では、洗浄・除去後に防カビコーティングや抗菌処理を施し、カビ菌が住み着きにくい環境を作るのです。また、施工時に建物の構造や換気の仕組みなどもチェックし、必要に応じて改善策を提案することで、長期的なカビトラブルの軽減を目指します。
とくに、肺カビ感染症やアレルギー体質の方など、健康被害が懸念されるケースでは、一度の施工でしっかりと原因を断ち切ることが大切です。中途半端な対策では、カビの胞子が再び室内に蔓延し、症状を悪化させかねません。MIST工法®は、カビの除去と防カビコーティングの両面から対策を行うため、単なる表面上の掃除や薬剤散布だけにとどまらない、抜本的な改善策を提供しています。その結果、長期的に安全で快適な空気環境を取り戻すことが可能となり、大切な家族や自分自身をカビの脅威から守る一歩となるのです。
2. 環境や健康に配慮した施工方法の特徴
カビ対策を行ううえで、気になるのが使用する薬剤や洗浄方法が環境や人体に与える影響です。実際、強力な洗浄剤や殺菌剤を使えばカビ自体は除去できるかもしれませんが、その一方で揮発性の化学物質が室内に充満することによる健康リスクや、建材へのダメージ、さらに自然環境への負荷などが懸念されます。MIST工法®では、こうした懸念を払拭するために、なるべく人体や動植物、そして地球環境に優しい薬剤を厳選し、施工後の安全性も十分に考慮した方法を採用しています。
具体的には、超微粒子ミストを用いた施工によって、建材の隅々にまで薬剤を行き渡らせると同時に、必要以上に大量の薬剤を使わなくて済むよう工夫されています。噴霧される薬剤の粒子を細かくすることで、少量であってもカビの根幹となる菌糸や胞子に直接アプローチし、高い除去効果を実現するわけです。さらに施工担当者は専門的な知識と技術を身につけており、現場の状況やカビの種類、建材の特性などを見極めながら、最適な濃度・時間で薬剤を使用します。その結果、施工後に薬剤のにおいや成分が残りにくく、生活空間に戻ったときに違和感や健康被害を感じるリスクを最小限に抑えられるのです。
また、MIST工法®はカビのみならず、細菌やウイルスの対策にも有効とされています。つまり、一度の施工で住環境全体の衛生レベルを高めることが可能となり、結果としてカビだけでなくさまざまな感染症リスクを低減できるメリットがあります。施工後には防カビ・抗菌コーティングが施されるため、その状態を長期間にわたって維持しやすくなるのもポイントです。建物の材質を傷つけず、住人にも優しい施工方法を選ぶことで、家族やペットが安心して暮らせる空気環境を守ることができます。環境と健康に配慮したMIST工法®だからこそ、カビ対策の最終手段としてだけでなく、予防策の一環としても注目されているのです。
まとめ:健康を守るためにできること
カビから身を守るために今すぐ始めたいこと:意識改革とプロの力で安心の住環境を実現
1. カビを「見えない脅威」として捉える大切さ
カビは、見た目に汚いだけの存在ではありません。家の壁や天井に生えている黒や緑の斑点を目にすると、「不快だな」と思う程度で済ませてしまうこともあるかもしれません。しかし、実際には目に見えないカビの胞子が空気中に大量に浮遊し、私たちの体内に入り込むことでアレルギー症状や呼吸器疾患を引き起こすリスクを高めています。特に免疫力が低下している方は、肺にカビが定着する「肺カビ感染症」やその他の真菌感染症を発症する可能性もあり、健康被害は決して軽視できません。
そのため、カビをただの汚れとしてではなく、「見えない脅威」として捉えることが非常に重要です。実際に目で見える部分が少ないからといって問題がないわけではなく、壁紙の裏や床下、エアコンの内部、収納スペースの奥などに潜み、胞子をばらまいているケースは珍しくありません。放置している間にもカビは少しずつ広がり、健康への影響はじわじわと進行していきます。早い段階で対策を講じれば被害を最小限に抑えられるのに、それを知らずに症状が重くなってからようやく対応を始める方が多いのが現状です。
また、私たちは日常的に「空気を吸う」行為をやめることはできません。その空気にカビ胞子が含まれていれば、誰でもそのリスクに晒されているということになります。だからこそ、自宅や職場など、普段の生活空間をいかに清潔に保つかが重要であり、カビが発生しづらい環境づくりを意識することが健康を守る第一歩となります。「カビは見える部分だけが問題ではない」という認識をしっかりと持ち、予防と早期の対策を心がけましょう。
2. カビバスターズ東海が提案する総合的なカビ対策
カビを根本的に予防・除去するには、「環境整備」と「専門家による的確な施工」の両面からアプローチを行う必要があります。カビの発生源を断ち切るためには、日頃から室内の湿度や温度を適切に管理し、こまめな換気や掃除を行うことは基本中の基本です。また、家具の裏側や押入れの奥、エアコンや換気扇のフィルターといった、見落としがちな場所も定期的にチェックすることで、カビの温床を未然に防ぎやすくなります。しかし、それでも一度カビが深く入り込んでしまった場合や、建物の構造そのものに問題があるケースでは、専門家の力を借りることが最善策となるでしょう。
カビバスターズ東海では、MIST工法®という特殊な技術を活用し、目に見えるカビだけでなく、素材の奥深くまで入り込んだ菌糸や胞子を徹底的に除去します。さらに、施工後には防カビコーティングを行うことで再発防止に取り組むなど、一度の施工で長期間にわたる効果を狙える点が大きな特徴です。単なる表面の漂白や殺菌にとどまらず、環境や人体に配慮した薬剤を用いることで、住みながらでも安心して施工を受けられるよう配慮しているのもメリットです。
また、カビの発生原因が換気の不足や結露など建物の構造にある場合、必要に応じて改善策の提案も行います。たとえば、壁や床の裏側の状態をチェックし、断熱材や換気経路の問題を解決することで根本的な湿気対策を行うのです。こうした総合的なアプローチによって、目に見えるカビだけでなく、将来的な再発リスクや健康被害の可能性を大幅に軽減できます。
「少しカビ臭いけど、それほど大きな問題じゃないかも」「換気をすればすぐに消えるはず」と楽観視していると、大切な家族や自分自身の健康を脅かす結果になりかねません。カビを見たら、あるいは異臭を感じたら、まずは専門家に相談することをおすすめします。カビバスターズ東海が提案する総合的なカビ対策は、あなたの住空間を清潔に保ち、肺カビ感染症などのリスクから身を守るための最良の選択肢となるでしょう。
----------------------------------------------------------------------
カビバスターズ東海 (名古屋本社・東京支店)
本社:名古屋市中川区本前田町44
東京支店:東京都品川区西五反田3丁目9番15号
フリーダイヤル 0120-147-215
----------------------------------------------------------------------