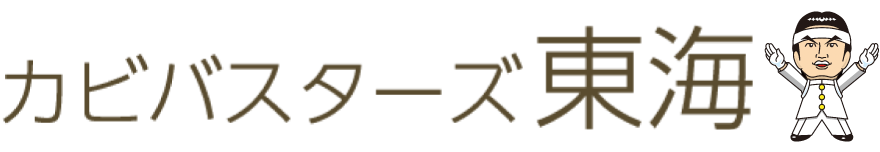ZEH・ZEBでも要注意!負圧が見えないカビトラブルの真実
2025/02/01
ZEH・ZEBでも要注意!負圧が見えないカビトラブルの真実
ダウンライトから侵入するカビリスクと、MIST工法®で実現する安心・安全な住まいづくり
こんにちは。MIST工法®カビバスターズ東海のブログへようこそ。 今回は「負圧」について、少し専門的な話をついでにご紹介いたします。断熱化や省エネルギー化が浸透、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)と呼ばれる、エネルギー効率に優れた建物が増えてきました。 断熱性能が高いことは冬でも暖かく、夏でも涼しく快適に暮らせるなど、多くのメリットがあります。 「排気」のバランスが崩れることによる「負圧」が一旦起こりやすいケースも見受けられます。
「負圧」とは、建物内の空気が外部よりも気圧が低い状態を通ります。 空気の流れというのは、高い気圧から低い気圧まで自然に移動するため、家の中が負圧の状態になると、隙間や口換気から外気や湿気がどんどん吸い込まれやすくなるのです。根裏や天井裏、壁の内部に湿気が発生し、想定外の場所でカビが発生しやすい環境が生まれている。が発生しやすく、内部に取り込まれた湿気がカビを引き起こしやすいのです。
私たちカビバスターズ東海は、MIST工法®によるカビ防除と、建物の通気バランスを考慮した対策で、お客様の住まいをカビの見通しから守るお手伝いをしています。対策を行うことで、見えにくい場所で進むカビトラブルを根本から防いでいきましょう。
目次
負圧(ふあつ)とは?
住宅環境を決める「気圧差」のしくみを知ろう
基本的な概念と建物内外の気圧バランス
建物の中に「負圧」が起こる背景には、室内と室外との気圧差が深い関係しています。大前提として、気圧は高いところから低いところへ移動する性質があり、空気は一時静止私たちが生活する住居やビルなどの建物では、室内外の温度差や換気システム、給排気設備の使用状況など、さまざまな弊害が重なり合って気圧差が生じます。 特に高気密・高断熱化が進むだ住宅では、従来の住宅に比べて空気の到来が取りにならないため、建物全体として換気のバランスが取りにくい状態になりやすいのです。
さて、レンジフードや換気扇など強力に外へ空気を排出しているとき、十分な量の外気を常に取り入れられなければ、室内の気圧は相対的に低くなります。 「入って、室内は外部よりも気圧が低い環境となるわけです。負圧になると、建物の隙間や通気口子どもの空気が外部から一気に流れやすくなり、そこに湿気や湿気、逆に、室内側の気圧が高い状態は「正圧(せいあつ)」と呼ばれ、外部に向かう空気が正圧・負圧いずれも、一時期に「良い」「悪い」とは言えませんが、その程度や住宅の設計意図によっては、考えぬ問題を考えて引き金にもなるのです。
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)のように、エネルギー効率を高めた建物は、室内の空調効率を高め、屋外との空気の入り口が大きくなるそのため、少しの不快で気圧バランスが崩れると、負圧状態が発生しやすくなります。思いついたことがあるのです。
負圧が住宅に及ぼす影響
建物内が負圧になると、一見すると空気の流れが室内に入ってくるだけなので、換気に有利なのではと思われるかもしれません。問題が発生するリスクがあります。恐れがあるのです。
まともなのが、ダウンライト周辺や天井裏などの、一見「目に影響のない空間」へのです。 照明器具のために空いた穴や隠れた配管の隙間から、負圧によって湿気の多い空気が吸い上げと、天井裏や壁の内部に湿気が高い状態が保たれやすくなります。 湿気はカビやダニなどの発生原因となるばかりか、木材などの建材を腐食させ、住宅の耐久性悪影響を与えかねません。 、あそこに漏れ出る空気が滞留することで局所的に結露が起きる場合もあります。結露はカビの成長を加速させる最大の検討の一つです。
さらに、負圧によって引き寄せられるものは湿気だけではありません。と、住まい手の健康を損なうリスクも高まります。 アレルギーや呼吸器系のトラブルに悩む方にとっては、負圧による影響をより真剣に考える必要があります
。問題は、割り切って「換気が足りない」というだけでは語りません。カビや害虫、建材の劣化などのトラブルを防ぐ近道です。 室内と室外の気圧バランスを意識し、必要に応じて換気設備の点検や調整を行うことができ、安心して暮らせる住環境づくりにつながります。
ZEH・ZEBで近い負圧の原因
省エネ性能を追求した住宅だからこそ起こりやすい「負圧」の落とし穴
高気密・高断熱住宅における換気のしくみ
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)のように、省エネルギー性能を最大限に高めた建物では、高気密・高断熱化が届き、室内外の熱やこれは冷暖房効率を高めたり、外気温の影響を抑えたり大きなメリットがあるのに対し、換気の仕組みをきちんと把握していないと、思わぬところで負圧などの問題がまずなくなるのです。
注意住宅の換気には、自然換気と機械換気の2つの方法があります。 自然換気とは、窓を開けたり、家の隙間の空気を入れ替える方式のこと。高気密住宅では、自然換気だけでは十分に空気交換ができないケースが多いため、計画的に空気の流れをつくるために、24時間換気システムや排気型の換気扇などを取り入れるのが一般的です。
さて、勝手システムが正しく設定されていない場合、排気だけが強く働いて室内の気圧が下がり、時には「負圧」が生じやすい構造になっている。そのため、本来であれば給気口などから必要量の空気を取り入れなければならない否、多少の理由(給気口のフィルターが目に入っている、設置数が適宜など)で十分に機能していないと、気圧バランスが崩れてしまうのです。圧力差が大きくなり、隙間やダウンライトなど小さな会話部から強制的に空気が入った状態が続きます。
高気密・高断熱住宅では、断熱と気密によってエネルギー消費が抑えられる方、従来よりも換気コントロールへの依存度が高まるという側面があります。原因となる「そこそこな湿気」や「汚れた空気」が建物内部に滞留しやすくなります。 エコでありながら健康的な暮らしを守るためには、吸気と排気の一時に目を配る、換気の仕組みを正しく運用していく必要があるでしょう。
吸気と排気のバランス破綻による問題点
高気密・高断熱住宅における「吸気」と「排気」のバランスが崩れると、さまざまな問題が顕在化します。換気扇やエアコンの排気量が大きいので給気が足りない場合、自然と室内の気圧が下がり、空気は隙間や開口部外から中へどんどん吸い上げられます。がちですが、実際には以下のようなリスクが潜んでいます。
まず第一に、外気とともに湿気や微粒子、さらには花粉や排気ガスなどの汚染物質までもが建物内部に入りやすくなります。 特に天井に設置されたダウンライトなどの対話部は目に見えない部分が多く、吸い込まれた空気の通り道となることで、天井裏に大量の湿気その結果、建材が湿気を含んでカビが発生しやすくなったり、木材が聞こえる原因にもなりかねません。 一度内部でカビが繁殖すると、定期的な清掃だけで対処しにくいケースが多く、大がかりなリフォームが必要になることもあります。
次に、住まい手の健康面への悪影響も降りません。負圧状態が続くと、人が実際に行う生活空間にも花粉やPM2.5などの細かい粒子が流れ込みやすくなり、アレルギー症状や呼吸また、外気温との差によって室内の一部で結露が起こりやすくなるほか、カビが発生すれば細胞が飛散し、室内環境がいそうな恐れがあります。 高気密住宅は一度汚染物質が入ると自然には抜けにくい性質を持つため、適切な換気計画とメンテナンスを覚悟と、快適なはずの住まいが住みやすいストレスを考える空間になってしまう可能性があるのです。
今の状況を気にするためには、吸気と排気のバランスがしっかり取れているかを定期的にチェックすることが大切です。 換気システムの動作確認や給気口の清掃、フィルター交換など、定期的にからこまめにメンテナンスを行うことで不具合の際を早期に把握でき、重大な損失圧トラブルを未然に防ぐことができます。ZEH・ZEBならではの高い断熱効果を相談しながら、健康でカビ知らずの住環境を維持するためにも、バランスの崩れに対する常にの注意は一時的に怠けないポイントと言われます。
ダウンライトから始まるカビ発生メカニズム
ダウンライトが潜む見えない落とし穴:負圧により広がるカビ被害の考察
天井開口部が引き金となる負圧のプロセス
ダウンライトなどの照明器具を設置する際に天井に解放される「会話部」は、実は負圧が生じやすい大きなポイントになっています。の空気が外へ逃げにくいという特徴があり、その分だけ排気に頼った換気方法が用いられることが一般的ですしかし、換気扇やエアコンの排気能力だけが強いと、室内の気圧は相対的に低くなり、一方「負圧」状態に陥り易くなります。空気の性質として、高い圧力から低い圧力へ自然と流れます進んでいくため、室内の圧力が低いほど、外部から空気が建物内部へ強く引き続く現象が起こりやすいのです。
ちょっと負け圧の現象が心配になる箇所の一つが、ダウンライトをはじめとした天井諮問部です。天井にぽっかりと空いた小さな穴は、見た目には照明器具で障害があるように感じられるかもしれませんしませんが、実際には器具の隙間や配線周りなど、細やかな通気経路が残されています。密閉性の高い空間に湿気や微粒子がこもりやすくなります。
ダウンライト周辺に危険した湿気は、なかなか外へ排出されにくいばかりか、照明器具自体や周囲の建材の温度差によって結露が起きます。結露が日常的に起こる環境下では、カビやダニなどの微生物が繁殖するための条件が揃いやすくなり、結果的にカビ被害を考えてしまうのです。っていても、負圧の影響によって想定される外の空気や湿気が入って、完全に回避できません。 ダウンライトのように「必要だから設置している」のが当たり前の設備でも、負圧トラブルまた、この天井天井部の負圧プロセスを知っておくだけでも、定期的な点検やメンテナンスの優先順位を高められるはずです。
湿気が多い理由とカビの育ち方
ダウンライトを取り付けた天井裏や屋根裏に湿気が降りやすい理由には、建物の気密性が予測した現代住宅の特徴だけでなく、空気の流れや温度差、そして結露などさまざまな課題が複雑に絡み合うあります。天井裏や屋根裏といった空間は、換気のための対話部が少なく、室内の空気や外気との温度差が大きくなる傾向があります。乾きにくい環境に閉じこもりやすいため、知らずのうちに湿度の高い状態が継続してしまうのです。
カビの発生には大きく分けて、①栄養源、②適度な温度、③湿度、④酸素の4つが必要とあります。住宅の建材には木材や石膏ボード、断熱材など有機・無機を問わず様々な素材が含まれていますが、それらの表面や内部にはホコリや油分、もしかしたら人の体からの微量な皮脂など、カビの栄養源となる物質が含まれていることがほとんどありません。カビ細胞が急速に繁殖する土壌が生じております。
特に天井や壁の内部は普段の生活空間から見ても痛くて、直接掃除する機会はほとんどありません。また、一度カビが根を録画してしまい、一般的な洗剤や市販の消毒用アルコールだけでは表面しか除去できず、建材の奥深くに残った菌糸が原因と再発するケースもよくあります。はダウン周辺に制限された話ではありませんが、負け圧で吸い込まれた湿気によって最初に影響を受けるのが天井裏であることを考えると、ダウンライトまわりの点検や早期対策こそが最大限重要になった結果的に、住宅の寿命や住みやすさを大きな要素にもつながるために、「負圧が起こると湿気が多くなる→カビが発生する」という一連の流れをよく理解して、定期的にような見回りとカビ対策を心がけましょう。
実例紹介:ダウンライト周辺に広がるカビ被害
写真が語るリアルな被害状況:見落としがちな天井裏のカビ進行
実際の写真から見るカビの範囲
実際にダウンライトの付近や天井裏にカビが発生した事例写真を目にすると、多くの方がその「広がるの早さ」と「被害範囲の大きさ」に驚きます。周辺の小さな黒ずみや点状の斑点が見られる程度でも、天井裏を点検してみると想像以上に奥までカビが繁殖していた特に高気密・高断熱住宅では、ライトダウンの発話部その間に控えめな湿気が天井裏に入りやすく、当面換気が届きにくい空間のため、カビが一度発生すると時間の経過とともに天井全体へ、さらには壁の内側へ向かってよく進んでいく可能性があります。
写真で確認できるカビの色合いは、黒やグレー、茶色が多いですが、種類によっては白っぽい毛のような菌糸が存在していることもあります。集合体)が形成されており、細胞子も周囲に飛散している状態同様も過言ではありません。イト辺りのカビが発端となり、戦略は配線周辺や断熱材の向こうまでカビが潜り込み、視界のないうちに広範囲に至るケースも見受けられます。や断熱性能の低下を考えることにも、住宅全体の耐久性を損なうリスクが高まるのです。
さらに、写真を拡大して見ると、カビの細胞子や菌糸が繊細に起こっている様子がわかり、これが原因で空気中にカビの細胞が漂い、室内環境や住居の健康を危うくする可能性がありますダウンライト周辺のわずかな黒ずみを「ちょっと汚れているだけ」と慎重になってしまうと、実際には天井裏で大規模に拡散しているかもしれません。早めの点検や対策が最も重要なことを念頭に置いておく必要があります。
初期症状を慌てるとどうなるか
カビ被害の初期症状としては、ダウンライトまわりの壁紙や天井クロスにわずかな変色や黒ずみ、あるいは軽いカビ臭が感じられることが挙げられます。 「一時的な湿気」などと見なれて放置されてしまうと、カビの繁殖は静かに、確実に進んでいきます。天井裏や断熱材の内部には届きにくいほど、換気が慎重である場合が多いため、一度繁殖を始めたカビが日日に勢力を拡大し、取り返しのつかないレベルまで広がることも少なくありません。
カビが多々増殖すると、まず建材へのダメージが大きくなります。 木材が腐朽して強度が落ちるほかに、石膏ボードや断熱材も劣化し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。カビの細胞や代謝物質が空気中に拡散されることで、住宅の室内環境が次第に悪化してしまう点も起こりません。 これらはアレルギー疾患や呼吸器トラブルなどの健康被害を考慮して、特に小さなお子様や高齢者がいる家庭では深刻な問題となるでしょう。
さらに、ダウン付近の天井裏から始まったカビは、壁内部や床下へも移行しやすく、トータルでのリフォーム費用や修繕コストが高額になるケースがあります。いる負圧の調整や、ダウンライト周囲の部分的な点検・施工だけで変える場合も多いですが、拡大が進むと天井一帯壁や一面を剥がしての大掛かりな工事が不可能になり、住みながらのリフォームが正義的なことも考えられます。ありますが、カビトラブルが一番負担を感じることになるでしょう。
「少しの黒ずみだから大丈夫」と楽に観ずに、毎日からダウンライト周辺の天井や壁、さらには室内の換気状態に関心を持ち、異変を感じた専門業者への相談を含めた早期対応を検討することが、カビトラブルを当面の留意点とさせていただきます。
MIST工法®カビバスターズ東海の対策
MIST工法®で叶える「根本的なカビ対策」と「負圧改善」の両立
MIST工法®によるカビ除去・防カビの仕組み
MIST工法®は、カビの発生源を把握し、除去から再発防止までを一貫して行うことを目的とした先進の工法です。残るまるため、内部に根を再現したカビの菌糸や細胞子が残りやすいMIST工法®では超微粒子のミストを建材の隙間や深部にまで行き渡ることで、目に見えない部分に潜む菌糸や細胞子までしっかりと処理し、根本的にからカビを退治するのが大きな特徴です。
さらに、ただカビを除去するだけでなく、必要に応じて防カビ剤を均一に噴霧し、施工箇所にカビが定着しにくい環境づくりにも重点を置いています。施工で長期的なカビ抑制効果が期待できるのはもちろん、建材そのものものの寿命を我慢し、住宅全体の耐久性を維持することも大きなメリットがあります。特にダウンライト付近の天井裏など、奥まった場所にカビが発生しやすいケースでは、超粒子ミストならではの高い浸透力が最大限に活きてきます。
施工時においても、MIST工法®では一切人体やペット、環境に配慮した薬剤を置くため、作業後の強い薬品臭や、長期的に残る刺激など少ない点も安心材料のひとつです。把握するためには、まず赤外線カメラやカビ検査キットなどを用いて発生箇所や広範囲を正確に診断し、その結果に基づいて最適な施工計画を提案しています。また、施工後は定期的な点検やカビの再発防止策のアドバイスも行い、お客様へがずっと安心して暮らせる住環境をサポートいたします。
今後総合的なアプローチにより、MIST工法®は「一時しのぎ」ではなく、「長期的に住まいの健康を守る」カビ対策を実現します。 特に、負圧の影響を受けやすいZEH・ZEBなどの高気密・高断熱住宅では、ダウンライトや配管周りにカビが入りやすいリスクが高いため、MIST工法®の利点がより重視されることになるでしょう。
負圧へのアプローチと根本的な解決策
カビを除去・防カビするだけでは、負圧が引き続き存在すれば、また別の不具合から湿気や外気が危険し、再びカビが発生してしまう可能性があります。建物が負圧にならないように」または「必要以上」 MIST工法®カビバスターズ東海では、施工時に負圧の原因を調査し、それを改善する対策まで提案することで、カビの再発を防ぐ総合的なケアを行っています。
負け圧を考えると最も多い原因の一つは、吸気と排気のバランスが崩れることです。 具体的には、換気扇やレンジフードなどの排気能力が強い限り、給気口の数や機能とりあえず問題を解決するには、まずは給気口や換気システムの設計を見直し、フィルターの清掃や部品交換、必要に応じた更新などを行って、排気量に見合った新鮮な空気が適切に供給されるように整備する必要があります。機やエアコンの使い方、定期的な窓開け換気のタイミングなど、生活習慣の面で見直すべき点も少なくありません。
ダウンライト周辺や天井裏でのカビ発生を根本から対策するには、建材の隙間がどの程度あるのか、断熱材が適切に配置・施工される期限など、施工品質のチェックが重要です。 ®カビバスターズ東海では、カビ除去の現場で今後の点を診断しながら、部分的な気密工事や断熱処理の改善を提案することもあります。住宅によっては大規模な工事が必要なケースもある一方、給気口の清掃や小規模の対話部補修など、比較的手軽な対策で改善できる例も多々あります。
最終的には、カビを一時的に「施工途中」と隣にして、住宅の通気環境を整え、再度カビが発生しにくい状態を考えることが何よりも大切です。MIST工法®でカビを除去した後、正しい換気や湿度管理を継続することで、ダウンライト付近を含めた住まい全体の空気が常に清潔で健康的に保たれ、負圧トラブルにも無縁の快適空間を実現できます。
負圧トラブルを防ぐポイント
トラブルを未然に防ぐための換気とメンテナンスのチェックリスト
正しい換気システムの導入とメンテナンス
近年、住宅の高気密・高断熱化が進んだことで、換気システムの成果たす役割はますます重要になってきています。特に、ZEHやZEBなどの省エネルギー性能を重視した建物では、少しの換気バランスの乱れが「負圧トラブル」をどうしても原因になりません。まずは大切なのが、まずは建物の構造や家族構成、生活スタイルに合った換気方式を正しましょう一般的には、第二種換気(給気・排気ともにで行う方式)、第二種換気(給気のみ機械で、排気は自然に行う方式)、第三種換気(排気のみ機械で、給気は自然に行う方式)などに分類されますが、それぞれにメリット・野球があり、建物全体の気密性や生存者の健康リスクなどを総合的に考慮して導入する必要がありますあります。
それに加えて、その後のメンテナンスを怠らないことも非常に重要です。 同様に給気口やフィルターが目に入ると、新鮮な空気を十分に取り込むず、排気ばかりが強い状態になってしまうことが多いですその結果、室内気圧が降下し、外気をダウンライトや窓枠の隙間から強制的に取り込む「負圧」状態に陥りやすくなるフィルター類は定期的に洗浄・交換し、通気口や換気扇の動作チェックを行うことで、効率的な換気を維持することができます。また、換気システム本体のメンテナンスには専門知識が必要な場合もあります。メーカーや施工業者の推奨する定期で点検を依頼し、不具合を早期に発見しておくことが大切です。
さらに、いくら換気システムが行われていても、日常の習慣が原因で室内環境がおかしい場合もあります。ただし、せっかくの機械換気が十分に機能しないこともあるのです。トラブルを防ぐ誠実策と言えます。
定期的な点検とカビ対策の重要性
カビ問題は、早期発見・早期対処が肝心です。目に見える場所であれば日常の清掃やチェックは比較的容易ですが、天井裏や壁の内側、ダウンライト周辺のようなは通常目にする機会が少ないほど、気づきにくい被害が進行してしまう恐れがあります。高気密・高断熱住宅では、そば的な「隠れたカビ」の発生リスクが高まるため、定期点検のスケジュールを組むことが非常に大切です。変動する時期には、専門家による点検を検討するのも有効な方法でしょう。
カビ対策と一言でいっても、除去・予防・再発防止など多面的に解決が必要です。ダウンライト付近のような対話部からカビが進んでいる場合には、まずは建材や断熱材に深く入った菌糸を問題に除去しないと、表面的なクリーニングだけでは根本解決にならないことが多くあります。もしあれば、再発までのスパンを長くするために、防カビ剤の塗布やカビが信頼できる環境(高湿度・停止した空気など)を作らない努力が必要です。MIST工法®のように、超微粒子のミストで隅々まで浸透させ、効果的にカビを除去・防カビ処理を行う手法は、目に見えない空間にも対応できるとして注目されています。
また、住宅全体の空気の流れを把握することで、負圧がどこで発生しているか、どのように湿気が滞留しているかを確認することもポイントです。動作していても、そこに小さな不具合が重なって負圧状態が慢性化する場合があります。定期的な点検では、換気経路や給気口、排気口などをトータルに見直し、必要に応じて清掃や調整を行うことが、カビ対策と同じくらい大切なのです。をおかげで、住宅の長寿命化と快適性、そして家族の健康を守ることができるのです。
まとめ・次回予告
カビへ発生を根本から予防、負圧トラブルに負けない家づくり
負け圧を覚悟 カビに強い住まいづくりを目指す
負圧が発生しやすい高気密・高断熱住宅のメリットは、断熱性能や省エネルギー効果の高さにより、一年を通して快適かつ経済的に余裕点にあります。外部からの湿気や微粒子が大量に引き込まれ、天井裏や壁内部といった目に見えない場所でカビが繁殖しやすくなるリスこれから、「負圧のリスクをゼロにすることは難しい」という現実を、住宅手も施工業者もまずは「覚悟」しておくことが肝要です。実現するためには、建物内部の空気の流れを把握しつつ、定期的な点検やメンテナンス、適切な換気設備の管理が欠かせません。
優先ダウン付近は、照明器具をライトのために天井に発話部が設けられることから、外気の流入経路になりやすいポイントです。 さらに、照明の熱や結露などの影響を受けやすく、湿気がこもるとカビの繁殖の温床になりません。有効です。
また、各家庭のライフスタイルや季節ごとに異なる生活パターンに合わせて、換気を意識的に行う工夫も必要です。室内の湿気を逃がすことで、カビ発生の抑制につながります。給気口やフィルターの汚れが溜まると性能が落ち、結果的に負圧が強くなってしまうこともありますので、こまめな清掃や点検を怠らないようにしましょう。の土台となり、負け圧を覚悟しやすい条件を整えておかないための大切なステップなのです。
今後のメンテナンススケジュールの立て方や、よくある質問へのヒント
負け圧に重大な問題を解決するカビを未然に防ぐために、住まいの健康を維持するためには、定期的なメンテナンス計画をしっかり立てることが大切です。取扱説明書やメンテナンスガイドをもう一度確認しましょう。や給気口のフィルター掃除、換気扇の動作チェックなど、日常的に行うべき簡易点検のタイミングや頻度が記載されているはずです。月1回、年1回といった区切りで実践していくのがおすすめです。
また、ダウンライト周辺や天井裏といった箇所は、実際に目視で確認し短いもの、カビトラブルが起きやすいポイントです。上は異常がなくても内部に湿気やカビの異常がないかをチェックできます。費用面が気になる方もいるかも知れませんが、大規模なカビ被害が起きてからの修繕費用に比べて、定期点検のコストは大事で必要ケースが多く、結果経済的に負担の軽減にもつながります。
さらに、よくある質問としては「どのような換気方法が最適か」「カビ防止に特化したリフォームはできるか」「薬剤や施工の安全性は大丈夫か」などが挙げられます。柔軟、第二種、第三種と住宅の設計や断熱性、築年数などによって適正が異なるため、専門業者と相談の上総合的に判断する必要があります。しては、カビが発生しやすい箇所の気密処理や断熱性能を高める工事が効果的ですが、その際に合わせてカビ防施工を行うことで、再度の再発リスク低減を図ることも可能です。 、施工時に使用する薬剤や方法について不安を感じる方は、事前に具体的な製品名や安全性データを確認し、納得した納得して施工を依頼しましょう。
今回のヒントを参考に、無理のない範囲で日常的なメンテナンスと専門家による点検・施工を行うことで、家族が安心して暮らせる「負圧に負けない住宅環境」が整います。的な施工事例や費用の目安、DIYでできる予防策などについてもご紹介しますので、どうぞお楽しみに。
----------------------------------------------------------------------
カビバスターズ東海 (名古屋本社・東京支店)
本社:名古屋市中川区本前田町44
東京支店:東京都品川区西五反田3丁目9番15号
フリーダイヤル 0120-147-215
----------------------------------------------------------------------